Trip To Movie Locations : Nomugi Pass
写真・エッセイ/織田城司 Photo & Essay by George Oda
夏は高原の散策が気持ちいい季節です。今回のロケ地探訪コラム『名画周遊』は、明治時代に飛騨から信州の製糸工場に働きに出た女工の足跡をたどります。
信州岡谷
◾️和と洋のもてなし


信州にある明治の住宅の中に、きれいな障子がある。
障子の中の曇りガラスは模様入りで、よく見ると、模様は障子ごとにちがい、落ち着いた和室に優雅な雰囲気が漂う。

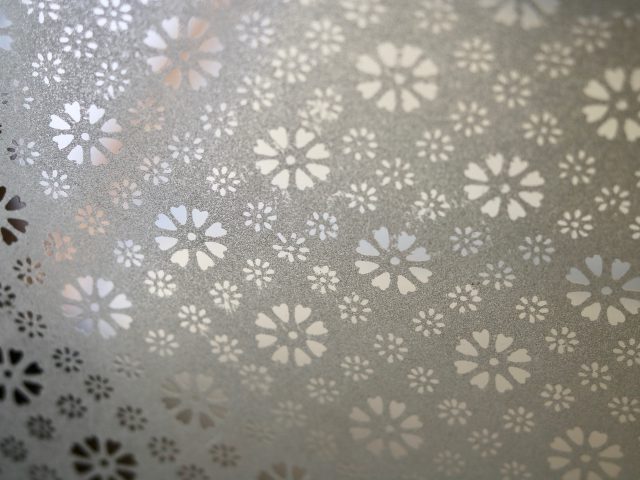

この障子のある住宅は、長野県岡谷市にある重要文化財「旧林家住宅」である。
明治30年に着工した住宅で、内装には、金唐紙など、当時最高の技術で作られた装飾が随所に見られる。

















この住宅には、玄関がもうひとつある。洋館の玄関である。明治の実業家は、外国人バイヤーをもてなすために洋館で迎えた。
まず、相手の文化に敬意をはらい、その後、和室に案内して日本文化を堪能していただくことが、接待の作法であった。






ところで、外国人バイヤーがわざわざ信州の山奥を訪ねる目的は何だったのか。当時世界最高の生産高を誇った日本の生糸の生産現場視察と、買い付けのためであった。
「旧林家住宅」を建てた林国蔵も、そんな製糸会社を経営する社長のひとりであった。

旧林家住宅の絢爛豪華な建築は新進の気風にあふれ、岡谷の製糸業がいかに大きな規模であったかを物語る。
廊下の欄間のデザインは、蜘蛛の巣のように見えるが、製糸業に欠かせない糸車に見えた。

諏訪湖畔の岡谷は、乾燥した空気と豊富な水系が繭の貯蔵に適し、古くから製糸業が盛んな地域であった。
明治になると、群馬県の富岡製糸場で近代製糸工業を学んだ技術者や女工が岡谷で製糸工場を相次いで開業する。明治13年(1880)になると、横浜から輸出する生糸の量は長野県が群馬県を抜いて1位になった。


岡谷の製糸工場は、諏訪湖に注ぐ天竜川周辺に集まっていた。明治37年(1904)から始まった日露戦争が終わると、アメリカ向け輸出景気で急速に工場が増え、水車動力から石炭の火力に転じたボイラーの大煙突が林立して、「諏訪の千本煙突」と呼ばれるようになった。
街中には、煙突に加え、マンションのような4〜5階建ての建物も多く見られた。これは生糸の材料になる繭を貯蔵した倉庫で、生糸の生産量がいかに多かったかを物語る。
◾️女工でにぎわった糸都

製糸業全盛期の昭和5年(1930)、国勢調査によると、岡谷市の人口は54,800人。このうち工場内の女工は約30,000人であった。
街は休日を謳歌する女工であふれ、駄菓子屋や芝居小屋、映画館などが栄えた。特に正月休み前は、帰省土産を買う女工でにぎわった。







◾️生き証人の記録

岡谷の製糸工場で働く女工を一躍有名にしたのは、山本茂実が昭和43年(1968)に発表したノンフィクション文学『あゝ野麦峠』である。
山本茂実は足掛け5年、かつて女工の経験がある老女を訪ね、当時の様子を聞き取り、まとめたのが本作である。訪ねた老女の数は三百数十名に及んだ。

『あゝ野麦峠』は発売されると、たちまちベストセラーになった。当時は高度成長時代と言われたが、庶民の暮らしは豊かにならず、不平不満が爆発して、デモやストライキが多発していた。
こうした世相の中、資本家と労働者の葛藤を描いた骨太なノンフィクションは、庶民から多くの支持を得た。その後、昭和54年(1979)に映画化されると、さらに野麦峠が広く知られるようになった。

山本茂実が『あゝ野麦峠』を執筆しようと考えた動機は、昭和43年(1968)にむかえる「明治百年」にあったという。明治百年を自分なりに表現しようと考えていた時、思い浮かんだのは、かつて祖母から聞いた野麦峠の話だった。
その話によると、毎年何万人という飛騨の女性が、信州の製糸工場で働くために、歩いて野麦峠を越えた。片道約160㎞の道のりを3泊4日かけて歩き、冬は雪山越えであった。山本茂実はそんな女工の目から見た明治史を書こうと思った。

山本茂実が調査を続けて気づいたのは、製糸業の元手になる原料と機材は、全て国内で調達できたことである。このため、出来上がった生糸を輸出すると、外貨獲得効率は100%であった。こうして獲得した外貨は明治政府の財源を支え、その資金で輸入した軍艦は日露戦争の勝利に貢献した。
ところが、その生糸を作った女工の功績を語る者は誰もいなかった。そこで、山本茂実は、明治の日本を支えたのは、教科書に登場する偉人ばかりでなく、庶民の力もあったことを、伝えようとしたのである。
◾️ある女工の悲劇

『あゝ野麦峠』の映画版は、大竹しのぶ演じる女工を中心に描かれている。この女工「政井みね」の物語は実話をもとに作られ、役名も実名がそのまま使われた。
みねは重病を我慢して働くうちに危篤状態になった。工場はみねの家に、すぐ誰か引き取りに来るようにと電報を打った。みねの兄、辰次郎は夜も寝ないで歩き通し、二日間で工場にたどり着いた。映画はこの兄を地井武男が演じた。

辰次郎はみねを背板に乗せて故郷を目指すが、野麦峠で飛騨の街が見えると力尽き、「ああ、飛騨が見える」と言い残して息を引き取った。享年20歳。明治42年(1909)の冬であった。
みねが働いていた工場は、映画では仮名になっていたが、原作では「山一林組」と実名で記してある。同社は明治12年(1879)に林瀬平が創業した大手製糸会社である。大正10年(1935)年に建てられた事務所と守衛所が残っている。

この事務所と守衛所はみねが通った頃より後に建てられたものだが、ここをイメージにして、辰次郎とみねが工場を去る場面を原作から引用する。
【山本茂実著『あゝ野麦峠』より】
“ 辰次郎は病室に入ったとたん、はっと立ちすくんだ。美人と騒がれ、百円工女ともてはやされた妹みねの面影はすでにどこにもなかった。やつれはててみるかげもなく、どうしてこんな体で十日前まで働けたのか信じられないほどだった。”

“ 病名は腹膜炎、重態であった。工場では辰次郎を事務所に呼んで十円札を一枚握らせると、早くここを連れだしてくれとせきたてた。工場内から死人を出したくないからである。辰次郎はむっとして何かいいかけたが、さっきいったみねの言葉を思い出してじっとこらえて引きさがった。
「兄さ、何もいってくれるな」
みねはそういって合掌した。飛騨へ帰って静かに死にたがっているのだと辰次郎はすぐ察した。みねはそういう女だった。”

“ 準備してきた背板に板を打ちつけ座ぶとんを敷き、その上に妹を後ろむ向きに座らせ、ひもで体を結えて工場からしょい出した。作業中で仲間の見送りもなく、ひっそりと裏門から出た。
辰次郎は悲しさ、くやしさに声をあげて泣き叫びたい気持ちをじっとこらえて、ただ下を向いて歩いた。しかし、みねは後ろ向きに背負われたままの姿で、工場のほうに合掌していた。”

“ その時、「おお、帰るのか、しっかりしていけよ、元気になってまたこいよ!」あとを追ってきた門番のじいさんが一人だけ泣いて見送ってくれた。
「おじさん、お世話になりました」
「元気になってまたこいよ、心しっかりもってな」
二人はお互いに見えなくなるまで合掌していた。辰次郎はこの門番の言葉にやっと救われた思いで歩き続けた。それはこの岡谷にきてはじめて聞く人間らしい言葉だったからである。”

辰次郎がみねを背負い、歩いて目指した家は、飛騨の角川(つのがわ)という集落にあった。辰次郎はまず野麦峠を越え、山を下ると高山や古川の街を経て、角川に至る約160㎞の道のりを9日間かけて踏破した。強靭な体力と気力には驚くばかりである。
辰次郎は飛騨に帰る道で何を見たのであろうか。その足跡を追って、岡谷から角川まで車を走らせた。
野麦峠
◾️街道の難所

野麦峠は標高1672m。岐阜県と長野県の県境にある野麦街道の難所である。
野麦峠に至る県道39号線は、古い車道らしく、道幅が狭くて対向車とすれ違うのに苦労する。

女工が野麦峠を越えた時代に車道はなく、山の斜面にへばり付く獣道のような旧野麦街道があるだけであった。この道は一部が残っていて、ハイキングコースとして利用されている。
雪の中、ここを歩いていた女工が足を踏み外し、斜面の下に滑り落ちると、一緒に歩いていた女工たちが、ほどいた帯を結んでロープがわりに使って救出した話は、旧野麦街道を歩くと、にわかに真実味を帯びてくる。


野麦峠の頂上にある「お助け小屋」は天保12年(1841)、山の遭難者救助の目的で建てられた。明治になり、女工が野麦峠を越えるようになると、無くてはならない休憩所として活躍した。
当時一人で小屋を切り盛りしていた「鬼ババさ」と呼ばれた老女は、女工の印象に残ったらしく、原作でも面白く紹介されている。映画では北林谷栄が演じた。


辰次郎は山本茂実の取材に、みねが野麦峠で死んだ時、お助け小屋の鬼ババさに励まされたおかげで飛騨まで連れて帰れたと答えている。
お助け小屋はその後、製糸業の衰退とともに閉店。昭和53年(1978)に『あゝ野麦峠』原作本のヒットと映画化の影響で再建された。小屋の周辺にはゆかりの品が展示されている。




お助け小屋では、土産物の販売や飲食のサービスがある。なかでも、「野麦そば」は土着の山菜やそばを使った素朴な一杯である。
柔らかい平打ちのそばを箸で口にはこぶと、きざみ海苔と醤油が香る。汁はだしの旨味をメインにして、甘さと辛さは控えめ。山菜の塩気と歯ごたえがアクセントになる、あっさりした味わいだ。

野麦峠は真夏でも20度ほどで、半袖だと肌寒く感じる。夏以外の季節なら、なおさらであろう。このため、野麦峠に着いた人は、まず「あたたまりたい」と思う。
そんな時、すぐに体の芯からあたためてくれるのは汁物。特に野麦そばは、柔らかいそばと、あっさりした汁で食べやすく、すぐあたたまる。ふやけたきざみ海苔は、そばと山菜をつなぎ、喉越しにふくらみ感をもたらし、あたたかさを増すことに貢献している。




飛騨高山
◾️繁華街の明暗

女工が飛騨に帰省した時の楽しみは、高山や古川の繁華街で晴れ着を買うことであった。呉服店では、押し寄せた若い娘が我れ先を争って「おじさん、あれ見せて、これちょうだい」と言いながら、一年の賃金としてもらった、指の切れるような新札を次々に出した。
店主は度肝を抜かれたが、気を取り直すと、この商機を逃すまいと、歳末、初売りの特売に加え、信州の工場に行く前の「支度売り出し」や、豪華景品の福引を企画した。
そんな繁華街も、遺体となった女工には冷たく、みねを背負った辰次郎を泊めてくれる宿は無かった。辰次郎は仕方なく、昼間は農家に頼み込んで納屋で休み、夜間に人目を忍んで歩いた。














飛騨古川
◾️女工の集合場所

飛騨古川にある八ツ三旅館は、かつて飛騨の女工が信州に出発する時の集合場所として利用された。
みねもここで近所の仲間と集合して信州に旅立った。ここまで来ると、みねの家がある角川の集落も近かった。

製糸工場の人事採用担当者は、女工の野麦越えを引率して、暮れはそのまま八ツ三旅館に宿泊して年を越した。年が開けると、女工の家に挨拶に行き、契約更新の手続きをすることもあった。
初売りの日は、女工を連れて街に繰り出し、ご馳走を振る舞った。うっかり女工から目を離すと、他社に引き抜かれてしまうからだ。近代工場とはいえ、生産ラインは人海戦術に依存していた。このため、人材確保は売上の生命線だった。









角川
◾️山の暮らし

辰次郎とみねが生まれ育った角川は小さな集落で、産業の90%は農業。辰次郎の家も例外ではなかった。辰次郎の健脚や体力は、野山を動きまわる農作業で培われたものであろう。
角川は山の斜面が川までせまり、田畑の面積はわずかだった。冬は雪に閉ざさる期間が長く、農業だけで生計を立てることが厳しく、常に食糧難であった。

そこに、信州の製糸工場から山高帽にトンビのコート姿の人事採用担当者が現れ、主人に「おたくの娘さんを、ぜひ我が社の工場でお預かりしたい」と言って、手付金の札束を差し出した。
こうして、みねは13歳で工場に奉公に出された。やがて、キャリアを積み、20歳で亡くなる直前は、優秀工女として年収百円まで登りつめた。当時の百円といえば、新築の家が一件建つほどの価値があったという。みねの死後、妹も信州の工場に出稼ぎに行った。


角川に高山本線の駅ができたのは、辰次郎がみねを背負って帰宅した25年後の昭和9年(1934)であった。それまで、女工の野麦越えは続いた。
野麦峠の話は、昔話として読みきれない深さがある。社会機構や労働環境など、いつの時代にも通じる問題が含まれている。そして、困難な時代を生き抜いた人々を通して、日本人を考えるのである。



政井みねの死後、日本の製糸業は全盛期をむかえた。
だが、昭和4年(1929)にアメリカから始まった世界恐慌の影響で糸値が暴落すると、輸出の低下で国内の株価も暴落。多くの企業が倒産して、街は失業者であふれた。

その後、景気は回復することなく世界大戦に突入。生糸の生産は縮小され、製糸工場は軍需工場に業態転換するか、休業や廃業に追い込まれた。
戦後、生糸の生産は再開したが、昭和48年(1973)のオイルショック以降は減少の一途をたどる。やがて、平成になると、国内の生糸は生産量より輸入量が上回るようになった。

山一林組は戦後、精密機械工業に業態転換したが、昭和47年(1972)年に閉業した。工場の跡地は現在、ショッピングモールの駐車場になっている。
唯一残された大正時代の事務所と守衛所は、日本の製糸業の歴史を物語る貴重な遺産として、国の登録有形文化財に指定された。


